今回はハンガリーにある家で乾燥大豆を使って納豆を作りました。保温器は持っていませんが、ヨーロッパの家に備え付けられている、セントラルヒーティングのヒーターを利用して、保温工程を組み込みました。作った納豆の変化を写真でまとめたので、参考になれば嬉しいです。
乾燥大豆から納豆を自作してみた
用意したものと工程をまとめます。大豆の量については各自お好みの量で構いません。また、今回は大豆を茹でて納豆を作りましたが、蒸し大豆でも美味しく作れます。
用意したもの
・乾燥大豆
・納豆1/2パック
・大豆を茹でる鍋、水
・熱湯1Lくらい
・ガラスボウル
・かき混ぜるスプーンや棒、あれば水切りざる
今回はハンガリーにあるアジアショップで購入した乾燥大豆を使いました。少し小粒なベトナム産の大豆です。価格は1kgで約1000円でした。

作り方
①大豆をたっぷりの水につけて一晩おく
写真の量で乾燥大豆300gくらいです。大豆が水を吸って膨らんでいたら完了です。
大豆を戻すときは腐りやすいので冷蔵庫に入れることをお勧めします。また、お急ぎの場合は熱湯で戻すと3、4時間ほどで完了します。


②新しい水を大豆の4〜5倍ほど入れて、大豆を茹でる
⇨沸騰するまで中火、沸騰してから弱火で大豆が柔らかくなるまで茹でる。少し柔らかめの方が良い。
⇨吹きこぼれないように注意する。また、途中で鍋の水が少なくなったら水を足す。

私は普通の鍋で茹でたので柔らかくなるまで3時間近くかかりました。
マルチクッカーの豆モードでは約90分かかりました。
③使用する容器と器具に熱湯をかけ消毒する。消毒後は自然乾燥させる
④納豆を冷蔵庫から出して常温にしておく
⑤大豆が煮えたら、お湯を切って容器に入れる
⇨水気が多すぎると納豆の粘りが薄まってしまいます。
⑥大豆が熱いうちに軽く混ぜた納豆を入れて全体に納豆の粘りを移すように混ぜる。
⑦ラップをしてヒーターの上に置き、24時間保温する
⇨温度の目安は40〜45℃、発酵の目安は24時間程度。

⑧冷蔵庫で一晩寝かせ完成
完成した納豆の写真
保温が終わった段階でかなり糸を引いており、冷蔵庫で一晩寝かせたらしっかり粘りのある納豆が完成しました。
1日目と5日目の納豆の様子を写真でまとめます。参考になれば嬉しいです。
完成から1日目
粘りは納豆そのものですが、味はまだ大豆感が強かったです。においはもう完全に納豆でした。


完成から5日目
粘りは1日目と変わりませんが、大豆が熟成され、より納豆らしい見た目になりました。発酵が進んだからか大豆が若干柔らかくなり、食べやすくなりました。においは1日目と変わらずでした。


納豆の味は
前回、発酵工程を入れずに作った時よりも納豆の粘りが増して、お店で買ったものに近くなりました。
1日目は大豆感が少しあったものの、寝かせるごとに納豆の味になっていきました。しっかり粘っていて美味しかったです。
ちなみに、今回出来上がった納豆は冷蔵庫保管をし、8日かけて食べ切りましたが、腐ったりお腹を壊したりすることはありませんでした。
海外での手作り納豆の美味しい食べ方
海外にいると納豆は作れても、なかなかタレまで用意することができません。そんな時の私のおすすめを紹介します。気になった味付けがあったら挑戦してみて下さいね。
・そのまま食べる
⇨自分で作ったから愛着もあってそのままでも美味しいです。しっかり大豆の味を感じられます。
・醤油+酢+ごま油
⇨まさに餃子を食べているかのよう。本当に美味しいのでぜひやってみて欲しいです。
・めんつゆ+すりごま
⇨胡麻和えみたいになって食べやすいです。めんつゆがないときは醤油を入れます。
乾燥大豆から納豆を作るときの注意点3選
実際に納豆作りをした筆者が考える、より美味しい納豆を作るために注意することを3つあげます。
特に発酵中の乾燥は納豆の出来栄えに大きく影響しますので注意が必要です。
・乾燥大豆はたっぷりの水で戻し、豆が指で潰せるくらい柔らかめに茹でる。
・腐敗を防ぐため保温による発酵は最大でも24時間を目安にする。
・発酵中は空気が入って納豆が乾燥しないようにする。
納豆の粘りが少ない時に考えられる原因5つ
保温が終わった時点で粘りが少ない場合、納豆菌がうまく増殖できなかったと考えられます。
うまく粘りが出ない原因としては以下が挙げられます。
・器具の消毒不足により納豆菌が雑菌に負けてしまった
・茹で上がった大豆の水切りが甘かった
・保温時に湿度の高い場所においていた
・発酵中に乾燥してしまった
・種となる納豆の量が少なかった
私も何度か失敗していますが、原因で多いのが2番目です。大豆に納豆菌を混ぜる段階で水分が多いと、粘りが水気で薄まってしまいます。少量ずつザルで水分をしっかり切ってから作った方が成功率が上がると感じました。また、湿度の高い場所で保温すると、発酵中に水分が増えて粘りが薄まってしまうので注意が必要です。
環境を利用して納豆作りを楽しもう
今回はヨーロッパのお家ならではですが、セントラルヒーティングを利用した納豆作りは、発酵に適切な保温ができ大成功でした。環境を活かして無理せず納豆作りを楽しみましょう。
↓もっと簡単に納豆を作ってみたい方はこちら↓
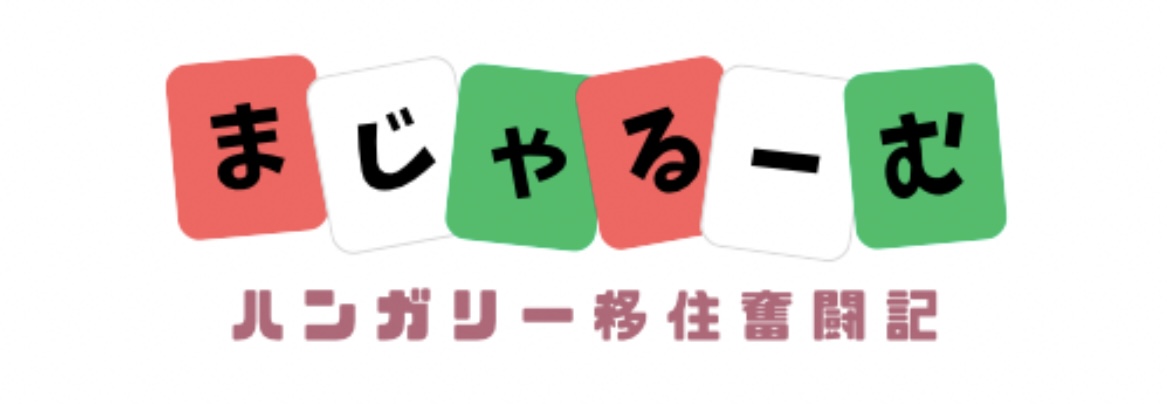


コメント